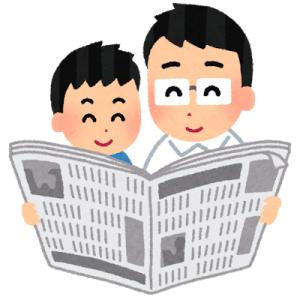意外と多い【父子家庭の割合】とは?あなただけじゃない!
周りを見ると両親と歩く子供の姿
そんな当たり前の光景がなぜか眩しく見えてしまう事はあるだろうか?
自分だけ…

私はそう思ってついついネガティブな気持ちになっていた
(今でもたまに思うのだが)
保育園に送り迎えに行っても周りの目が気になり窮屈な思いをしたり、買い物や遊びに行くと母親と一緒にいる子供を見ると自分の子に申し訳ない気持ちになったり…
自分だけ?という気持ちでいっぱいだったが、調べてみると意外と同じような人がいるんだなど思える理由があった
- PTA役員【父子家庭は免除】してもらえる?父子家庭に付きまとうPTA問題や断り方とは??

- 父子家庭の【養育費】に関しての疑問!金額の相場や支払率はどの位?
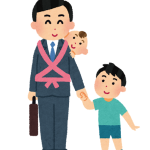
- 父子家庭と母子家庭はどう違う??ひとり親家庭の【支援や違い】について

- 父子家庭の【恋愛事情】!最近の傾向と父子家庭だからこそ考えないといけないこととは?
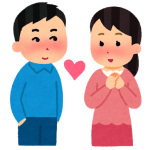
- シングルファザーを助ける【家事代行】!サービス利用するメリットや内容、相場とは??

- 父子家庭の【住民税】はどうなる?非課税世帯の対象になる?

- 父子家庭、【娘の生理の時】どうする??初潮の準備や知識について

- 父子家庭の大学進学、【授業料免除】などの大学進学支援対策とは??
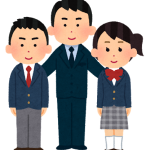
- 父子家庭の【デメリット】とは??父子家庭ならではの魅力もお伝えします!

- 意外と多い【父子家庭の割合】とは?あなただけじゃない!

- シングルファザーはなぜ【再婚しないのか】?恋愛、再婚が難しい5つの理由
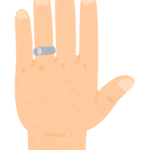
- シングルファザーの【住宅ローン】失敗しないための債務整理とは?

離婚率とその理由とは?
厚生労働省による「平成30年人工動態統計の年間推計」によると、平成30年の離婚件数は20.7万件
全世帯、全年齢を対象とした離婚率は約35%である
約35%ということは、三人に一人以上は死別、もしくは離婚しているということになる
意外と多い?!たしかに自分の職場でも離婚者はいるので、思っているよりも身近にそう感じているかもしれない
では、なぜ離婚率が高いのだろう
30歳〜34歳の離婚理由
理由① 経済的に余裕が出てくる
特に30歳〜34歳になると社会的地位も生まれて、経済的に余裕が出てくる
理由② 生活費を渡されない
妻側から夫が生活費を渡してくれない
18歳〜19歳の離婚理由
理由① できちゃった婚が多い
厚生労働省のデータによると15〜19歳でできちゃった婚をした人の割合は81.7%
まだ覚悟のない中での妊娠、結婚故に、離婚者も多いのではないか
理由② 金銭的余裕が無い
結婚、育児には想像以上にお金がかかり、その知識も無いまま結婚すると、様々な問題が重なって精神的負担になり離婚にいたってしまう
このように歳を重ねるごとに色々な原因が発生するようだ
離婚を防ぐためには、まず日頃から夫婦間の話し合う時間を作るようにし、お互いがどのような不満があるのか、どのように解消していくのかを考えることが大切なのではないだろうか
父子家庭の割合は?
同居を除く母子、父子家庭の割合は
父子家庭 11.3%
上の表は、ひとり親家庭の推移と割合の表である
これを見ると、ひとり親家庭の9人に1人は父子家庭の計算になる
確かに母子家庭は全体の9割なので多いと感じるが、父子家庭も確実に存在しているので、少なくとも父子家庭は自分一人だけではないのだ
しかし、そこにも壁は立ちはだかる
保育所や学校のPTAや懇談会、役員はほとんどが母親で構成されているため、すぐには輪の中に入っていくことができない
妻がいるときは長時間労働だったため、なかなか接点を持つことができなかったのだ
- 父子家庭の【育児仕事両立】は不安!ひとり親のパパ!仕事はどうしてますか?
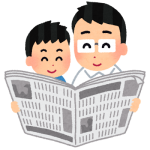
- シングルファザーを助ける【家事代行】!サービス利用するメリットや内容、相場とは??

- 父子家庭のための【年末調整】の書き方

- シングルファザーとして、【仕事と家事育児を両立】させるには?

- 父子家庭と母子家庭はどう違う??ひとり親家庭の【支援や違い】について

- シングルファザーはなぜ【再婚しないのか】?恋愛、再婚が難しい5つの理由
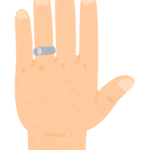
- 父子家庭は【つらい】?パパさん達の苦労やエピソードを紹介します!

- シングルファザーの【住宅ローン】失敗しないための債務整理とは?

- 【シングルファザーの再婚】は難しい?子供との新しい生活に向けて考える事とは
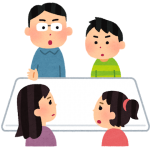
- PTA役員【父子家庭は免除】してもらえる?父子家庭に付きまとうPTA問題や断り方とは??

- 父子家庭、【娘の生理の時】どうする??初潮の準備や知識について

- 父子家庭でも【医療費免除】は受けれるの?? ひとり親家庭の助けになるひとり親家庭医療費助成制度とは

意外と多い父子家庭の割合とは?【まとめ】
こうした事実を一つでも知っていくことで自分だけがひとり親ではない、父子家庭ではないことが分かって頂けただろうか
様々な困難があるが、いずれにしろ子供を育てていくのは自分なので、少しでも心の負担を減らしつつ、日々の子育てを楽しめるようになって頂ければ幸いである